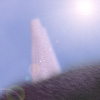|
|
昔むかし、あるところに ひとりぼっちの姫様がおりました 母を亡くして幾年月 迎えられた後添えの 后は姫を忌み嫌い 荒野の塔へと追いやって 暗く冷たい 白亜の塔 小さな窓から見えるのは どこまでも広がる空ばかり 一人寂しい姫様は 今日も窓辺で歌います この声が届いたなら 会いに来て 千と一の夜を越えて いつまでも 私は待っています 歌に惹かれてやってきたのは 一人の若き盗賊 幾多の罠を掻い潜り 現れた盗賊は 驚く姫に跪いて言いました 『荒野の果ての 白亜の塔に 素晴らしき声で歌う 銀の小鳥がいると聞き 海の彼方より 馳せ参じました 銀の姫君 王国の秘宝よ 私めは卑しい盗賊 捧げる剣も持たず 献じる宝物もありませぬ 唯一つ 貴女に贈ることのできるもの そう、我が至宝を捧げましょう』 それは自由という名の 何にも代えがたい宝物 そうして二人は 手に手を取って 自由の大地を 駆けたのです 「ところが、そううまくは行かなかったわけだ」 石壁に耳をぴったりとくっつけながら、老人はからからと笑った。 「え、そうなんですか?」 「そりゃもう、すべてが御伽噺のように『めでたしめでたし』で終わるわけがないじゃろ、小僧」 「そうよね。そんな終わり方なら、あんたがここにこうしているわけがないんだから」 容赦のない言葉に、老人はぴしゃり、と額を打つ。 「お嬢ちゃんの言う通りじゃな。あのままうまく言っておれば、わしゃ今頃、百人を超える子孫曾孫玄孫に囲まれてぽっくり行くのを待つだけじゃったろうて」 「どんだけ子供作る気よ、このすけべじじい」 呆れ声を人差し指で制し、コンッと壁を叩く。 それだけで、何の変哲もない石壁がゆっくりとせり上がり、秘密の扉がそこに現れた。 「当たり、じゃな」 眼を丸くする二人に、にやりと不敵な笑みを浮かべる老人。 「よし行くぞい。わしについてこい」 「は、はいっ」 柔らかな風に、エリカの花が揺れている。 アストアナ王国、首都アジェンタ。 隣国ルサンクは十数年続く内乱で揺れているが、アストアナはまだ傍観を決め込んでおり、故に国内は平穏そのものだ。 そんな穏やかな荒原の国に穏やかではない声が響いたのは、秋も深まったある日の午後のことだった。 「なんでわたしがそんなことに手を貸さなきゃなんないのよ!!」 語気も荒く言い放ち、さっさと席を立とうとする女魔術士に、部屋中から鋭い殺気が浴びせられる。 「ひええっ」 思わず腰が引ける少年だったが、魔術士の方はびくともしない。むしろ、喧嘩なら買おうじゃないのと言わんばかりに、ぐるりと辺りを見回してバチバチと見えない火花を散らしている。 小さな、しかし調度の整った応接間に集っているのは、性別も職種もバラバラな、物騒な気配だけが共通点という老若男女が合わせて十五名に、絹張りの長椅子から立ち上がってふんぞり返っている金髪の女魔術士と、その従者らしき少年。 そして、そんな両者に挟まれているにも関わらず、のんびりと茶をすすっていた最後の一人は、飼い猫の悪戯をたしなめるように口を開いた。 「こりゃ、やめんか、みっともない」 しわがれた老人の声に、霧散する殺気。しかし、剣呑な目つきはそのままに、彼らは口々に言葉を募らせる。 「しかしご隠居」 「このアマ、『そんなこと』とか抜かしましたぜ!?」 「大体、本当にこんなのが腕の立つ魔術士なんですかい?」 「アタシの方が美人じゃないの」 「そもそも、どうして俺らを連れてってくれないんです」 狭い応接間で一斉に喋り出したものだから、まるで鳥の巣をつついたような騒がしさだ。 「えーい、うるさいっ!」 堪りかねた魔術士が怒鳴りつけて、ようやく静まり返る室内。 そこで恐る恐る、少年が口を開いた。 「えーっと、あの。先代ギルド長さん、とお呼びしていいんですか」 「堅苦しいのう。『ご隠居』くらいにしておくれ。面倒なら爺さんでええわい」 「じゃあ爺さん」 魔術士がそう言った途端、再び吹き上がる殺気。それを見事に無視して、彼女は呆れ果てた口調で続けた。 「なんで、わたしらがあんたの恋路の手伝いをしなきゃなんないのよ!」 その言葉に、目の前に座る禿頭の爺、もとい先代盗賊ギルド長『鷹の目』は、七十歳とは思えないほど引き締まった細身の体を不気味にくねらせて、 「いやぁ、恋路なんて言われるとわしゃ恥ずかしいのぉ〜」 とのたまったのであった。 「やはりのお、お話のようにうまくは行かないのが人生じゃて」 粉々になった石の魔物を踏み台に、踊り場から上を角灯で照らしながら、老盗賊はしみじみと語る。 「それでもなあ。会った瞬間、互いに一目惚れしたところまでは良かったんじゃ。まるで御伽噺みたいだとわしも思ったくらいでな。しかし、そこからがまずかったんじゃなあ」 手に手を取って駆け落ちしてみたものの、すぐに追っ手に捕まって、二人は塔へと連れ戻された。 姫の懇願で命だけは救われたものの、彼は荒野に放り出され、姫は再び塔に閉じ込められて、不遇の日々を送ることとなった。 恋の逃避行は、たったの一日。それが、五十年以上前のことである。 「何度も再挑戦しようと頑張ったんじゃが、あれ以来警備が厳しくなっちまってなあ。そうこうしているうちに国王一家が相次いで病で亡くなって、王位継承者の姫さんが担ぎ出されて……、あれよあれよという間に、女王陛下の誕生よ」 しかし。御輿のように担ぎ出された女王陛下は、ただのお飾りではなかった。 彼女は誰もが目を剥く政治手腕で、後継者争いで荒れた国内を治め、諸国と巧妙に渡り合った。それまでたびたび対立していた隣国ヒーシュテルンとの和解を成功させ、ヒーシュテルン王家から婿を取って男児を産み、厳しく、そして愛情を持って育てた。 そうして、王子が妻を娶り、二人の間に生まれた子供らが成人するまでを待って、老齢を理由に王位を息子に譲った彼女は、悠々自適の隠居生活を始め――るのかと思いきや、彼女が選んだ隠居先は、荒野に立つ塔だった、というわけだ。 「す、凄い方ですね……」 「まったく、いい根性よね」 荒野にぽつんと佇む、入り口から最上階まで罠だらけの塔に、齢七十の女性が一人暮らし。よほど肝が据わっていなければ出来ない芸当だ。 「わしが惚れ込むのも分かるだろう?」 相好を崩す老盗賊に、呆れたと鼻を鳴らすリダ。 「悪趣味にもほどがあるわ。付き合わされるこっちの身になれっての」 ああもう、と悪態をついて杖を振り上げれば、先端の宝玉から放たれた光が階上からごろごろと落ちてくる巨大な岩を打ち砕く。 「ギル! ちゃんと調べてから歩けって言ってるでしょうが!」 「ご、ごめん、おかしいなって思ったんだけど、足ひっこめるのが間に合わなくて」 まさか階段の一歩目に罠が仕掛けてあるとは思わなかった。冷や汗を掻く少年に、老盗賊はなになに、と笑ってみせる。 「誰だって、そうやって経験を積んで大きくなるんじゃよ。なぁに、お前さんは筋がいい。きっといい盗賊になれるだろうて」 「い、いや、盗賊はいいです……」 「この調子じゃ、経験を積む前に罠の餌食よ。まったく、一体、幾つ仕掛ければ気が済むのさ!」 ここまでは、一つの階に一つの罠が仕掛けられていた。故に、単純に考えればあと十個だが、油断は禁物だ。 「ほっほ、腕が鳴るのう。現役を退いて長いこと経ったが、まだまだ若いもんには負けんぞい」 「何言ってんのよこのくそじじい! さっきから罠を見つけてんのはギルじゃないの!」 「その罠を解除しとるのはわしだぞ? 見つける人間、外す人間、壊す人間。役割分担は大事じゃよ」 しらっと言ってのけ、老盗賊は憤るリダにぱちりと片目を瞑ってみせた。 「お前さん達に頼んで、本当に良かったわい。わしの目は確かだったろう?」 そう、人を見る目はあるつもりだった。 だから、その少女を一目見た途端、恋に落ちた。 『私をさらっても、いいことなんてないわよ』 突然の侵入者に、顔色一つ変えずに言い放った、年若い姫。 『でも……私がいなくなっても、きっと誰も困らないの』 僅かに震えた声が、彼女の寂しさを雄弁に物語った。 『ごめんなさい、泥棒さん。ここには何もないから、あなたに何もあげられないのよ』 そんなことはない、と首を振れば、姫は不思議そうに首を傾げてみせた。 『ここにあるのは孤独だけ。他に何があるというの?』 「あなたがいる」 背後から響く懐かしい声に、はっと顔を上げる。 本を手に揺り椅子から立ち上がれば、窓から上半身を覗かせた老盗賊は、おどけた仕草で帽子を上げてみせた。 「やっと見つけた。我が姫君」 「やっと来たのね、私の泥棒さん」 窓枠をひょいと飛び越え、揺り椅子の前までやってきて、老盗賊は優雅に一礼してみせた。 「銀の姫君、王国の秘宝よ。私めは卑しい盗賊、捧げる剣も持たず、献じる宝物もありませぬ。唯一つ、貴女に贈ることのできるもの――。そう、我が至宝を捧げましょう」 「あなたはそんなこと、言わなかったわ」 腕を組み、そっぽを向く老婦人に、老盗賊はにやりと笑って帽子を被り直す。 「覚えててくれたか。嬉しいのう」 「ま、いやあね、そんな年寄りじみた喋り方で」 「仕方あるまいよ、もうお互い、いい年なんじゃ」 わざとらしく咳払いをして、片手を伸ばす。 「荒野の塔に秘められたお宝、この『鷹の目』が確かに頂いた。さあ、行こう! 我が姫君」 「ええ、いいわ。世界の果てまで連れて行って。私の泥棒さん」 五十年の時を超えて、恋人達が微笑みあう。 そうして、二人は手に手を取って―― 「えーっと、お楽しみのところ大変申し訳ないんですが」 気まずそうに割って入った声に振り向けば、窓の外にひきつった笑みを浮かべた少年と、不貞腐れた顔の女魔術士が浮かんでいた。 「まあ、どなた?」 小首を傾げる恋人に、老盗賊は自慢げに胸を張る。 「強力な助っ人じゃよ。これだけの罠を攻略するのは一人じゃ難しいと踏んでな。手を貸してもらった」 「……というわけなんですが、すいません、最後の罠を外しそこなっちゃって……」 「早くしないと崩れるわよ。この塔」 あらまあ、とおっとり呟く老婦人。 「だから窓から入ってきたのね?」 「いやあ、まさか最後の最後で、塔が倒壊するような大掛かりな罠を仕掛けてるとは思わんでなあ」 「まあ、いいわ。この塔にはもう未練もないし。さあ、行きましょう」 裾をからげて窓枠に足をかける老婦人の勇ましさは、五十年の時を経て少しも色褪せることなく。 「あなた達、冒険者ね? 申し訳ないけど、下まで送ってくださる?」 「は、はいっ」 「なんでわたしがこんなことしなきゃいけないのよ……。ほら、早くつかまって!」 「これで良かったのかな……?」 倒壊する塔を眺めながら呟くギルに、リダはふんと鼻を鳴らして、少し離れたところで佇む二人に目を向けた。 「いいんじゃないのー? 依頼はちゃんと果たしたんだし」 いつになく投げやりな口調に苦笑しつつ、楽しげな笑い声に耳を傾ける。 五十年ぶりの再会だ、積もる話もあるだろう。 「なんだかお邪魔みたいだし、もう行こうか」 「そーね。依頼料はギルドの方からふんだくればいいんだし。あーもう、ご馳走様!!」 わざと大声を出してみたものの、見つめあう恋人達の耳には届かなかった様子で、更に不機嫌になるリダをまあまあ、と宥めながら、ギルは伝説の恋人達を振り返った。 「なんか、色々お話と違ってたけど……素敵な再会だったね」 「……ま、本人達が幸せなら、それでいいんじゃない」 さあ、もう行くよ、と歩き出したリダを追いかけようとして、背後から響いてきた「こりゃ小僧!」という声に、ぎょっと立ち止まる。 「何も言わずに行くんじゃない。まったく、最近の若者は薄情じゃのー」 エリカの花を掻き分けてやってきた彼に、いやさっきリダが声かけたんですけど、とも言えずに黙っていると、老盗賊は目を細めて、少年の顔をじっと見つめてきた。 「あの、俺達もうおいとましようかと――」 「小僧」 少年の言葉を遮って呼びかけたものの、何か考えるように黙り込んだ老盗賊は、躊躇いがちにこう続けた。 「お前さん、ギル=ローバーと言うたな」 「え? ええ」 「父の名は、ダンか?」 言い当てられて、思わず目を見張る。 「そうですけど……どうして――」 「いや、なに。ちょっとした……知り合いでな」 僅かに口ごもり、そして老盗賊は懐かしそうにギルを見つめた。 「いやな、ふとした仕草が似とるんで、もしかしたらと思ったんだが……そうか、ダンの息子か」 「はあ……」 なんと答えていいか分からずに困っていると、老人はますます目を細めて、囁くように告げた。 「気をつけた方がいい。忘れておらん者が、まだ残っとる」 「え?」 きょとん、とする少年の肩をぽんぽんと叩き、つまらんことを言った、と笑い飛ばす。 「いや、忘れてくれ。年寄りの戯言だ。さあ、わしらはこれから、中断された蜜月旅行に出発じゃ! 門出を祝っておくれ」 「は、はいっ、ってええっ!? これからすぐに蜜月旅行って……」 展開の早さに目を白黒させていると、空から大量の花びらが降ってきた。 「おお、きれいじゃのー」 「あらまあ、綺麗だこと」 「祝ってあげるから、さっさと蜜月旅行でも婚前旅行でも行ってきなさいよ! ほらギル、あんたはこっち!」 ぐいと首根っこを掴まれて、老盗賊から引き離されたギルは、むすっとしたリダの顔を見上げて、もしかして、と呟いた。 「羨ましいの? リダ」 「そんなわけないでしょ! こんな気の長い恋愛なんて、わたしにはできっこないんだから」 ますますむっとした顔で、それでも花を降らし続けるリダに、あははと笑う。 「リダも長いこと恋人いないし、ちょっとは羨ましいんじゃ――ぐへっ」 「あほなこと言ってないで、もう行くよ!」 少年の鳩尾に拳を叩き込んで黙らせると、リダは恋人達にくるりと背を向けた。 「それじゃあね、爺さん。折角恋人と会えたんだから、ぽっくり行くんじゃないよ」 「心配せんでもわしは百まで生きるつもりじゃ。世話になったの、お嬢ちゃん。小僧と仲良くおやり」 「余計なお世話!! ほら、ギル! しゃきっと歩く!」 「む、無理……」 銀の姫君 王国の秘宝よ 私めは卑しい盗賊 捧げる剣も持たず 献じる宝物もありませぬ 唯一つ 貴女に贈ることのできるもの そう、我が至宝を捧げましょう それは自由という名の 何にも代えがたい宝物 「さあ、行こう! 我が姫君」 「世界の果てまで連れて行って。私の泥棒さん」 そうして二人は 手に手を取って 自由の大地を 駆けたのです 終☆
|