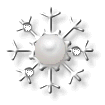|
|
「36 etude」 22:「告白」
覚えているのは、涙に濡れた漆黒の瞳 ごめんね ごめんね 何度もそう繰り返していたのは、誰だったのか 「あら、起きた?」 気だるげに寝台から体を起こす青年を振り返って、女は艶やかな笑みを浮かべた。 「随分うなされてたけど、大丈夫?」 「ああ……昔の夢を、見てた」 何度も繰り返し見る、幼い頃の夢。それは、途切れ途切れの記憶を無理やり繋ぎ合わせたような、実に粗悪で後味の悪いもの。 「また、あの夢なの」 付き合いの長い女は、その一言だけで内容を察し、労わるような視線を向けた。 ――嫌な夢さ。 最初に問いただした時のことを思い出す。当時まだ少年と呼べる年齢だった彼は、心配そうに尋ねる女に向かって、それはもう苦々しく呟いたものだった。 ――涙に濡れた瞳。自分とよく似た、漆黒の…… ごめんね、とひたすらに繰り返す女 何と言えば、泣き止んでくれたのだろう どうすれば、笑ってくれたのだろう……? 「ここんとこ、しばらく見てなかったのにな……」 悪いことが起こる予兆じゃなきゃいいが、と軽口を叩いて、その話題を打ち切る。そして青年は、窓に張り付くようにして外を眺めていた彼女に、ふと問いかけた。 「何見てるんだ?」 その言葉に、女はまるで子供のようにはしゃいだ声を出す。 「見てごらんなさいよ、雪! 初雪じゃない?」 「へぇ……」 床に落ちていた上着を拾い上げ、肩に掛けて寝台を抜ける。そうして女の隣に寄り添うようにして、青年は窓の外を覗き込んだ。 「随分とまあ、積もったもんだ」 「そうね。ほら見て、気の早い子供がもう雪遊びに夢中になってるわ」 銀化粧を施された街角に転がる、不恰好な雪だるま。そのそばでは、子供達が雪合戦に夢中になっている。 「元気ねえ」 「子供だからだろ」 「あらま、あんただってまだまだ子供じゃないのよ」 くすくすと笑い声を上げて、女は窓辺を離れた。粗末な寝台へと戻り、脱ぎ散らかしてあった服を掻き集める。 「ほら、ちゃんと着ないと風邪ひくわ」 むっとしながら服を受け取り、面倒そうにそれらを身につけ始める青年。 「子供扱いするなよ、俺だってもう成人してるんだぞ」 「だったら叱られるようなことするんじゃないの。お客さんに風邪引かして帰らせたとあっちゃ、店の看板に傷がつくってもんよ」 へーへー、とぼやきつつ、上着の襟を留める。堅苦しい黒装束だが、不思議と彼にはこの上なく似合っていた。まるで、この服を着るために生まれついたかのように。 「ま、この店がどうなろうと、知ったこっちゃないんだけど」 商売熱心な彼女らしからぬ発言に、おやと眉をひそめる青年。そんな彼を見つめ、女は寝台に腰掛けたまま、おずおずと口を開いた。 「あのね、あたし……結婚するの」 意外な告白に目を見開き、そして青年はかすかな笑みを浮かべる。 「……そっか。そりゃ、良かった」 「あら、少しは残念がってくれると思ったのに」 からかうように言ってやると、青年はにやり、と人の悪い笑みを浮かべて答えた。 「勿論、残念さ。でも、あんたが決めたことなら、俺がどうこう言うもんじゃない」 突き放すような言葉。それでも、それが彼の優しさであることを、女は知っている。 だから女は、こう続けた。 「あのね、相手はね、駆け出しの学者さんなの。半年くらい前かしら、同僚に無理やり引っ張ってこられたらしいんだけど、そりゃもう初心で可愛かったのよね」 付き合いで来たのなら、二度と逢うことはないだろう。そう思っていたのに、彼は再び現れた。顔を真っ赤に染めて、それでも自分の意思で扉をくぐり、彼女の目の前に。 「お給金少ないっていうのにさ、頑張って来てくれるんだもの。そりゃ嬉しかったわよ。でもまさか、結婚を申し込まれるなんて夢にも思わなかった」 彼女自身の年季はとうに明けている。それでもこの商売を続けていたのは、他に出来ることなど何もなかったから。 「彼がね、言ったの。『家に帰って、君が笑顔で迎えてくれる。それ以上の幸せはない』って」 乙女のように頬を染め、女はうっとりと言葉を紡ぐ。 「あたしには何もない、何も出来ないと思ってた。でも、そんなあたしを必要としてくれる人がいるって、そう思ったら、なんだか嬉しくてさ」 だから、と女は黒髪の神官を見上げて言った。 「あたし、幸せだわ」 透き通るような笑顔に、小さく頷く。そして青年は少し照れくさそうに、こう囁いた。 「笑ってるあんたが、一番好きだ。だから幸せになってくれ。悲しい涙を流さないで済むように」 ――それはきっと、伝えられなかった、少年の思い。 だから別れの涙を堪えて、その細身の体をぎゅっと抱きしめる。 「さよなら」 「ああ。元気で」 滑らかな頬に、祝福の口づけを。 そうしてくるりと踵を返し、足早に去っていく青年の姿を眼に焼きつけながら、女は叫んだ。――朗らかに。歌うように。 「ラウル! あんたも――あんたもいつか、幸せになりなさい!」 随分と乱暴な、そして心からの言葉に振り返り、青年はああ、と笑ってみせる。 「約束は出来ないが――まあ、努力はしてみるさ」 不敵な笑みに、あどけない少年の笑顔が重なって見えたのは、堪えた涙の仕業か。それとも、初雪がもたらした小さな魔法か。 「幸せに、なりなさい」 去り行く背中に呟いて、女はそっと――全ての思い出に別れを告げるように、扉を閉じた。 終☆
|